妊娠や出産には、予想以上にお金がかかることがあります。
健診や入院、出産費用に加えて、交通費や薬代など…いつの間にか大きな出費に。
でも実は、それらの支出の一部は、「医療費控除」という制度を使えば、確定申告を通じて税金の一部が戻ってくる可能性があります。
ただしこの制度、年末調整では対応してもらえないため、自分で申請しないと受け取れないという落とし穴も。
この記事では、妊娠・出産に関する医療費控除のしくみや、対象になる費用、そしてふるさと納税との意外な関係まで、わかりやすく解説します。
医療費控除とは?家族の医療費を合算して申告できる制度
医療費控除とは、1年間(1月~12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合、税金が安くなる制度です。
ポイントは「家族分をまとめて申告できる」こと。対象になるのは、以下のような支出です:
- 生計を一にする家族の医療費(本人・配偶者・子ども・親など)
- 1年間の自己負担医療費が10万円超(所得200万円未満なら所得の5%超)
- 控除上限は200万円
※控除は「課税所得」から差し引かれるため、年収が高い人ほど効果が大きいという特徴もあります。
妊娠・出産で対象になる支出は意外と多い
妊娠や出産に関わる支出も、医療費控除の対象になるケースがあります。
控除対象になるもの(例)
- 妊婦健診の自己負担(助成券でカバーできなかった分)
- 正常分娩(自然分娩)にかかる出産費用
- 帝王切開や吸引分娩などの医療処置費用
- 医師の指示による薬や検査
- 通院や出産時の公共交通機関の交通費
- NICU(新生児集中治療室)などの新生児治療費
- 不妊治療(自由診療含む)
対象外になるもの(例)
- マタニティグッズ(妊婦帯、サプリ、抱き枕など)
- ベビー用品(オムツ、哺乳瓶、チャイルドシート)
- 里帰り出産の旅費
- 医師の指示がない美容目的の処置
- 差額ベッド代(希望による個室など)
出産育児一時金などの補填は差し引かれる
医療費控除の注意点として、「実際に自己負担した金額」だけが対象になります。
たとえば…
出産費用が60万円
出産育児一時金で42万円の補填あり
→ 差額の18万円だけが医療費控除の対象になります。
同様に、会社からの出産補助や医療費の補填がある場合も、その分は控除額から差し引かれます。
一方で、「お祝い金」や「用途が自由な一時金」のようなものは、差し引く必要はありません。
実際にいくら戻る?妊娠・出産の控除額をシミュレーション
ケース例:
- 妊婦健診や出産にかかった総費用:62万円
- 出産育児一時金:42万円支給
- 実質の自己負担:20万円
医療費控除の対象額は:
20万円 − 10万円(または所得の5%)= 10万円
課税所得が10万円減ると、税率10%+住民税10%と仮定して、約2万円が戻ってきます。
確定申告のために、家計簿アプリで記録を
医療費控除の申請には、「誰に・いくら払ったか」の明細をまとめる必要があります。
領収書の提出は不要になりましたが、医療費の明細書は原則として作成が必要です。
我が家ではマネーフォワードMEを使って医療費の支出を自動で記録しています。
カード連携やレシート読み取り機能を活用すれば、年末にまとめて振り返るのもスムーズ。
ふるさと納税との兼ね合いを考える上でも、日頃からの記録が重要です。
医療費控除とふるさと納税、意外な落とし穴
ここで意外と知られていないのが、医療費控除を使うと、ふるさと納税の控除上限が下がる可能性があるという点。
ふるさと納税の上限額は「課税所得」によって決まるため、医療費控除で所得が減ると、寄付できる額も減ってしまいます。
さらに育休などで年収自体が下がっていると、控除上限はさらに低くなります。
上限オーバーを防ぐための対策は?
- 詳細シミュレーションを使う
ふるさと納税サイトには「医療費控除などの反映」が可能な詳細版があります。簡易版では正確な金額が出ません。 - 年内の寄付は12月上旬までに調整を
12月末ギリギリで調整するのは危険です。11月時点で概算、12月下旬に正確な寄付額を把握すると安心です。 - 医療費は家計簿アプリで管理する
何にどれだけ使ったか、すぐに集計できる状態にしておけば、ふるさと納税と医療費控除のバランスもとりやすくなります。
まとめ:妊娠・出産は医療費控除のチャンス。確定申告を忘れずに
妊娠・出産でかかる医療費は意外と多く、しかも自費になる部分も少なくありません。
それを確定申告で取り戻せるかもしれない制度が、医療費控除です。
ただし、年末調整では申請できないため、確定申告が必要。
ふるさと納税の上限にも影響するので、医療費の記録と年末の寄付調整はセットで行うのがおすすめです。
申請しないと受け取れない「隠れた給付金」のようなこの制度。
妊娠・出産という大切なタイミングだからこそ、忘れずに活用して家計の支えにしていきましょう。
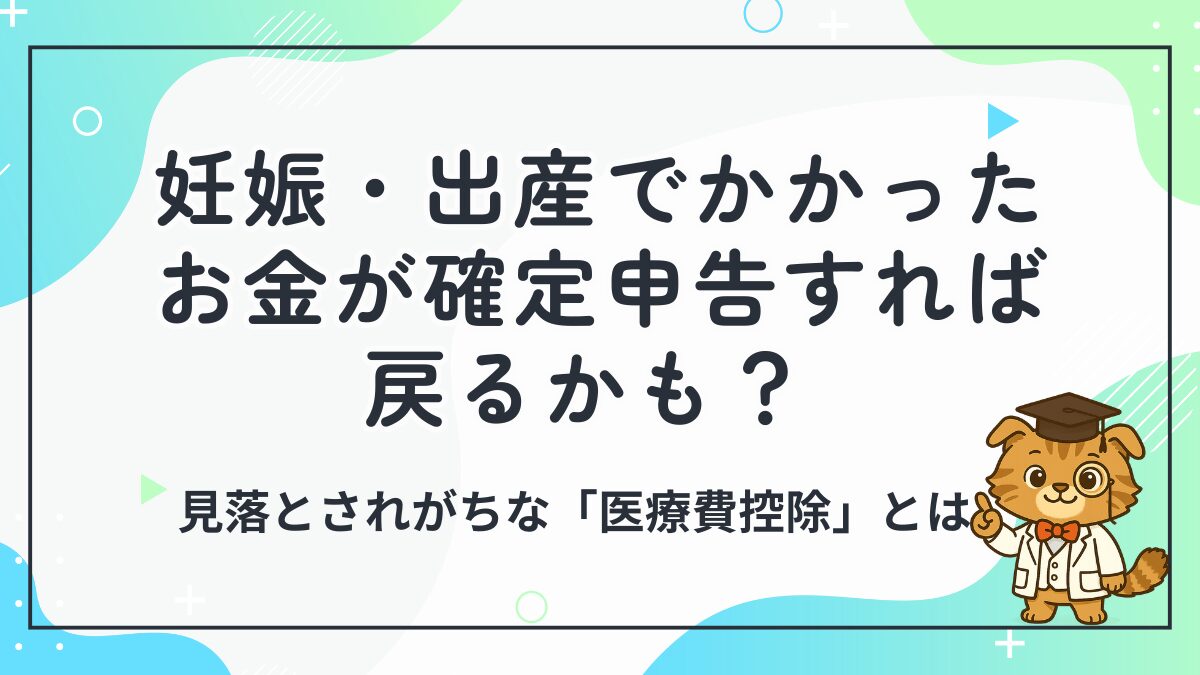

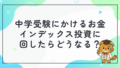
コメント